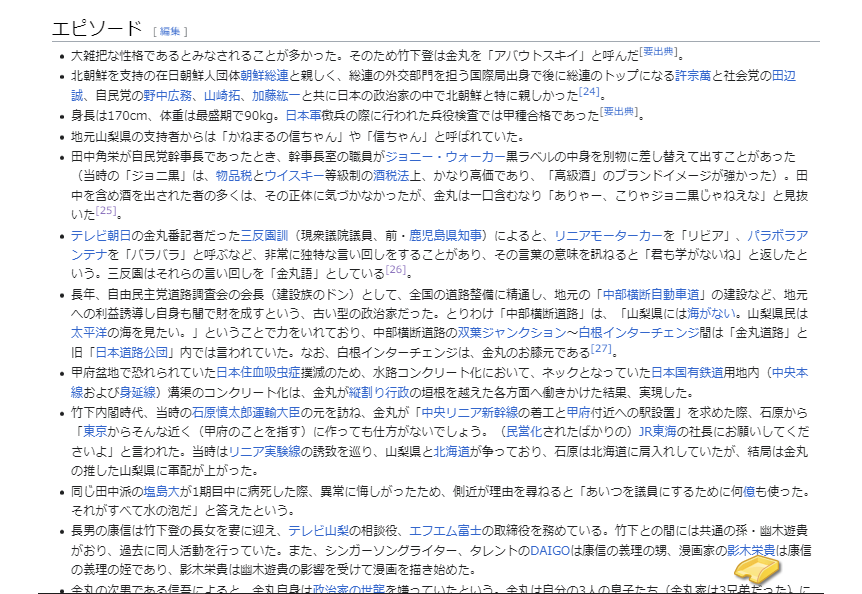さて本書については既に書評等も出尽くしており、その文章の丁寧さ、わかりやすさ、親しみやすさは読んでいて非常に心地よい。本作者による編著書(「近代出版研究 創刊号」)と同様、いくらでも複雑に表現できる題材を平易に調理しながら、しかし薄味になることなくそのおいしさを凝縮する事に成功している良書であった。
という事で、せっかくの機会なので本書を元に俺も調べる事にしよう。本ブログの読者はご存知のように俺は「世界のラブコメ王」であると同時に政治好き・政局好きであり、特に「三角大福中」だとか「経世会支配」だとかに興奮するのでそっち方面で調べる事もあるわけであるが、「三角大福中」とはつまるところ田中角栄、「経世会」とはその田中角栄に反旗を翻した竹下登による派閥である。その竹下登という歴史的政治家に隠れて今では知る人ぞ知る存在となったが金丸信という政治家がいて、竹下も面白い政治家だが金丸は更に面白い政治家であった。浪花節や義理人情を前面に押し出しながらも天性の勘によって日本政治を左右し君臨し、自民党幹事長・副総裁、或いは副総理まで歴任した、見方によってはとんでもない政治家なのであるが、実は長年気になる事があった。それは何か。まずはインターネットで調べる一番簡単な方法であるウィキペディアを見てみよう。
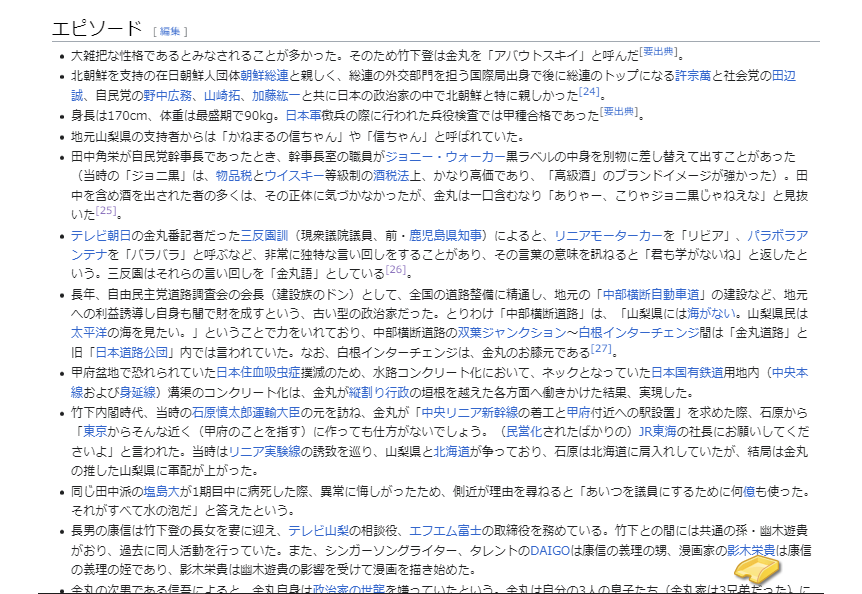
図1
ここで俺が気になっているのが「金丸語」(エピソードの6ポツ目)というもので、金丸信による有名な言葉と言えば防衛庁長官時代の「思いやり予算」、もしくは政局の節目でよく聞く「さすっているようで叩いている、叩いているようでさすっている」があるが、ここには、
『リニアモーターカーを「リビア」、パラボラアンテナを「バラバラ」と呼ぶなど、非常に独特な言い回しをする』
とある。そう言えば俺も何かの雑誌か本で「金丸は独特の言い回しをする。レベルをラベルと言ったり…」と書いた文章を目にした記憶がある。自民党幹事長等の要職を務めながら、或いは闇将軍・田中角栄に戦いを挑むという型破りで得体の知れない政治家でありながらそのようなエピソードがあるのは非常に面白い、他にどんな「金丸語」があったのか調べてみよう…となるわけだが、まずは自分の本棚から政治関係の本を探し、そこから更に金丸信のエピソードや人物評が書いてある部分を探すと以下が出てきた。

図2

図3
「リビア」「バラバラ」以外に「ビッグサービス(リップサービス)」が出てきた。一つ追加である。リップサービスを「ビッグサービス」というのは言い得て妙というか、リップサービスというのは大抵大げさなものだから、「ビッグサービス」でも意味している事は同じで、しかしやや下品な表現のような気がするが、それこそ金丸流である(もっと下品な表現に「大便より小便の方がましだ」がある)。
ちなみに俺は政治・歴史関係の本は100冊以上所持している。そのうち戦後政治史、それも金丸信が活躍した80年代~90年代前半の政治状況を追った本も50冊以上は持っているが、それらは「政治状況」についての記録であるから、金丸個人、もしくは政治家個人のエピソードを集めた本など当然ないわけである。ごく稀に「新たに政調会長に就任した〇〇氏は個性的な人物として知られる。例えば×××の時に△△△で…」といった挿話が文章に添えられる事があるが、それは本当に「添え物」でしかないので、そんなものを探して50冊の本を血眼になって頁をめくるのは時間的に大変で、また探せば必ずあるというわけでもない。
では次に、Yahooで検索しよう。もちろん「金丸信」で検索したら膨大な検索結果となってしまうので、「金丸信 AND リビア」で検索する。

図4

図5
当たり前だが先程のウィキペディア情報の二番煎じである。理想は『「リビア」以外にも、こんな金丸語があった』という情報が載ったホームページ等が検索できる事だが、そう簡単にはいきません。
ではいよいよここから本書を使用して調べる事にしよう。とは言えできるだけ簡単に、短時間に調べてしまいたいので、本書における「Googleブックスを使った調べ方」を実践する。ツールバーを「期間限定なし/21世紀/20世紀/19世紀…」から「20世紀」にして、更に「限定・全文表示」をして…

図6の1

図6の2

図6の3

図6の4
出てきた出てきた(図6の4)。「環境アセスメント」を「環境セメント」、「ご託宣」を「ごせんたく」。ほうほう…とは言え出典の雑誌名が「言語」(第18巻 213~216号)? 何だそれは、有名人の言語を集めた雑誌か? そんなもんがあるのか…でまたしてもYahooで「言語 雑誌」で検索すると…大修館書店によって2009年まで発行されていた雑誌で、言語の本質にせまる雑誌…ははあ、だから有名人(政治家含む)のちょっとした言葉も紹介されているのか、有名人の言葉がTV等を通じて言葉として既成事実化する事もまた言語をめぐる現象の一つですからな。

図7の1

図7の2
というわけでこの「言語」という雑誌に紹介されている金丸語も信用できるので、現在のところ金丸語は以下である。
・リビアモーターカー(リニアモーターカー)
・バラバラアンテナ(パラボラアンテナ)
・ビッグサービス(リップサービス)
・環境セメント(環境アセスメント)
・ごせんたく(ご託宣)
「ごせんたく」も言い得て妙である。ご託宣を頂く事で心が洗われる、つまり洗濯(せんたく)なのである。
また以上の言葉を探す過程で、「金丸語」が載っている本は以下がある事もわかった。ウィキペディアより「ニューステーション政治記者奮闘記/三田園訓」、Googleブックスより「金丸信 寝技師の研究/仲衛」、「教科書では教えない日本政治/栗本慎一郎」、そして雑誌「言語」。ではこれらの本を国立国会図書館に行って閲覧したら、「これ以外の金丸語は~」等の記載があるだろうか。多分ないだろう、もしあれば、またその新しい金丸語が今までにわかったもの以上に面白いものであれば既にどこかに出ているはずで、つまりこれは何のパラドックスだ? 「誰も知らない(或いはごく少数しか知らない)、しかし有益で貴重な情報」など存在しない、なぜなら有益で貴重な情報を誰も知らないわけがないからだ…。
まあそれはそれとして再び「調べる技術」に戻って別の調査方法を使ってみよう。「レファレンス協同データベース」である。俺以外の誰かが「金丸信という面白い政治家がいて、その政治家は独特の『金丸語』を駆使していたようだが、その『金丸語』とやらを具体的に知りたい」と質問して、それを記録に残してくれていればいいが、「金丸信 リビア」で検索しても結果はゼロであった(当たり前だ)。

図8の1
そこで単に「金丸信」だけで検索する。

図8の2
「金丸四原則」というものが出てきたが…大した事はない。こんな事は政治家であれば誰でも言う事である。↓

図8の3
というわけで「レファレンス協同データベース」では芳しい成果はなかったが、なに次がある。「件名」である。「NDL典拠」で「金丸信」を入力…おお、出てきました。

図9の1
1914年から1996年なので間違いない、これが俺の知りたい金丸信である。この「金丸信」をそのまま件名検索すればいい。

図9の2

図9の3

図9の4
11件。いい感じに絞り込まれた。更にタイトルを見れば…「金丸信のめざした日朝国交正常化」「権力の代償」「政治腐敗を撃つ」といった本に金丸信の微笑ましいエピソードが載っているわけがないし、載っていたとしても上記の「リビア」や「バラバラ」が紹介されて終わりだろう。金丸信の人間的エピソードが満載された本…という事であれば「昭和の信玄 人間金丸信の生涯」「金丸信:最後の日本的政治家 評伝」「金丸信 全人像」あたりが良さそうである。特に「昭和の信玄 人間金丸信の生涯」は2010年発行で、没後14年が経っているのだから人間的エピソードも期待できよう。「金丸信:最後の日本的政治家 評伝」「金丸信 全人像」となると発行年が1992年、1984年であり、まだ金丸が現役政治家だった時の発行で、味方も多いが敵も多かったこの政治家の人間的エピソードがふんだんに盛り込まれている本とは思えない。
ちなみに「金丸信 全人像」はデジタルコレクションの個人送信サービスで目を通したが、いわゆる阿諛追従本、饅頭本みたいなものであった。

図10
というわけで「昭和の信玄 人間金丸信の生涯」を国会図書館に行って借りてしまえばいいわけだが、そう簡単に国会図書館に行けるわけではない。国会図書館は日曜休館なのだ、しかし俺は土日休みという事になっておるが土曜は大体仕事をしておるのだ、何で日曜に休館なのだ…などと言ってもしょうがないですね、地元の公共図書館なら日曜にやっとるのでそこにこの本があれば…で「国立国会図書館サーチ」「Cinii」にて確認するも、もちろんこんな特殊な本が一般的な公共図書館にあるわけがありません。金丸ゆかりの山梨の図書館に行かねばならない(拓殖大学八王子図書館なら行けない事もないが)。

図11

図11の2
ところでその公共図書館ではよほど小規模な図書館でない限り新聞DBがあろう。本書によれば読売新聞(ヨミダス)がお勧めという事なので日曜日に地元の公共図書館に行って、使用手続きをして(指定管理者なのでまたしてもちんぷんかんぷん…いやこの話はやめておこう)検索、もちろん「金丸 AND リビア」で検索すると…おお、出てきた。

図12
読売新聞の2002年9月30日の夕刊に「新日本語の現場」という連載記事があり、そこに「リハーサル」を「リサイタル」、「タイムリミット」を「タイムメリット」と言っていた事が語られている。また記事では「リハーサルとは言え、一世一代の舞台。リサイタルの方が本質を言い当てている」「タイムリミットをタイムメリットと言い間違えたのも、与野党対立も時間が解決するという、国会の実態を知り抜いた氏ならではの言葉」という好意的な解釈もあり、やはり時間が経てば罵詈雑言を浴びせられた政治家の評価も変わってくるのだなあ…と思った次第。
ちなみに朝日新聞クロスサーチにも同じように「金丸語」の記事があった。やはり新聞というのはすごいですねえ。

図13
ここまでの「金丸語」を整理すると、
・リビアモーターカー(リニアモーターカー)
・バラバラアンテナ(パラボラアンテナ)
・ビッグサービス(リップサービス)
・環境セメント(環境アセスメント)
・ごせんたく(ご託宣)
・リサイタル(リハーサル)
・タイムメリット(タイムリミット)
となった。7つの言葉が国立国会図書館に行かずとも調べる事ができたわけで、まあ7個もあれば調べものとしては十分だが、しかしもっとあるかもしれない(ないかもしれない)。そのためには調査の過程で見つけた本を実際に読んでみよう…という事で何とか土曜に国会図書館に行ってきて、以下の本を確認する。
・ニューステーション政治記者奮闘記/三田園訓」
・金丸信 寝技師の研究/仲衛
・教科書では教えない日本政治/栗本慎一郎
・言語(雑誌)
・昭和の信玄 人間金丸信の生涯
・金丸信:最後の日本的政治家 評伝

図14

図14の2
確認したところ、やはり上記7つの言葉しかなかった。それも7のうち1か2しかなかったり、7のうち5はあったりで、しかし7つ全てを網羅した本はなかった。
それとは別に驚いたのは雑誌「言語」の当該箇所で、

図15
何と「1989年7月29日の毎日新聞から拝借」していたのである。そんな事はGoogleブックスには表示されていなかったぞ(図6の4)、まあ待て、せっかく国会図書館にいるのだから新館の新聞資料室に行って確認しよう、俺にとっては「永神秋門攻防戦」以来、国会図書館で一番親しみやすい場所だからな…というわけで急いで新聞資料室に入って、1989年7月の縮刷版を手にした。

図16
うへえ。よりにもよって新聞の1面に書いておったのか、という事は金丸のこの独特の言い回しというのは広く世間に認知されておったのだなあ。
で、ここまで調べてわかった事だが…ウィキペディアの記事にある「リビア」「バラバラ」よりも、「ビッグサービス」「ごせんたく」「リサイタル」「タイムメリット」といった金丸語の方が、より金丸という政治家の面白さや奥深さがわかるわけで、なぜこれらが載っていないのだろう。結局はウィキペディアはウィキペディアでしかないという事でしょうね。
というわけでだいぶ長くなりましたが、この「調べる技術」によって、わざわざ永田町の国会図書館に行かなくても、公共図書館ぐらいで目的は達成する事が証明せられたのであります。今後も本書を片手に色々と調べる事にしよう。
おまけ:国会図書館で「調べる技術」を読みながら調べる↓

図17